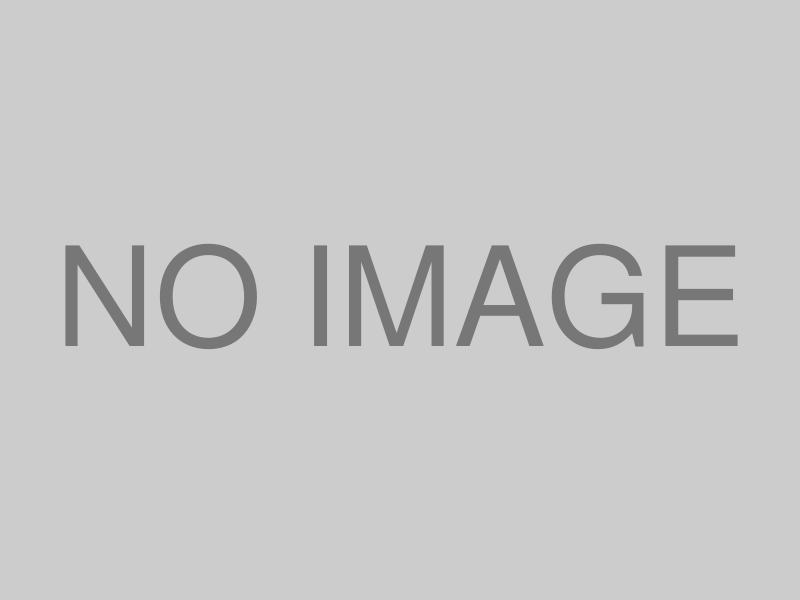債務超過とは?解消法についても解説します
目次
企業の会計上、収入のほうが支出よりも多い状態を黒字といい、逆に、収入よりも支出が多い状態のことを赤字といいます。
赤字の状態が続いていくと、いずれは、債務超過に陥ります。
債務超過とは、企業や個人の財務状況に関する用語で、資産総額が負債総額を下回る状態を指します。
つまり、債務超過の状態では、所有している資産を全て売却しても、負債を全て返済することができない状態になります。
債務超過になると銀行からの融資が受けづらくなったり、上場企業の場合には上場廃止になるなどのデメリットが生じます。
企業が債務超過に陥ると、その信用力が大きく低下するため、早期の対策が重要です。
債務超過の原因
1.赤字とは
会計では、通常、企業の利益は「収益-費用」で計算されます。
「収益-費用」がプラスの場合を黒字といいます。黒字の場合、「収益-費用>0」です。
一方、「収益-費用」がマイナスの場合は、赤字といい、「収益<費用」の状態です。
ある年に赤字が出た場合、それが翌年以降に持ち越されていき、何年にもわたって赤字が続くと、その総額が「累積赤字」になります。
この「累積赤字」は、帳簿上は貸借対照表の純資産の部に計上され、具体的には「利益剰余金のマイナス」が「累積赤字」の金額となります。
2.赤字が累積すると債務超過になる
利益剰余金は会社が獲得した利益、あるいは、損失の累積金なので、利益ができるとプラスになりますが、赤字が出るとマイナスに転じます。
そのため、会社の赤字が継続するほど、利益剰余金のマイナス金額である「累積赤字」も増大します。
この累積赤字の金額が年々増大していくと、いつかは資本金の額を超えてしまいます。この状態が「債務超過」です。
債務超過は通常、企業が営業活動で十分な利益を上げられず赤字が累積した場合のほかに、借入企業が過剰に借入を行い返済能力を超えて負債が膨れ上がった場合や、不動産や設備などの資産の価値が下落した場合、資産総額が減少し、負債に対して不足した場合にも発生します。
累積赤字が発生する理由
企業の累積赤字は、収益よりも支出が継続的に上回っている場合などに生じます。具体的には、以下のような状況が原因となることがあります。
1. 継続的な営業損失(高い固定費)
企業が長期にわたって売上よりもコスト(仕入れ、人件費、設備投資など)が上回っていると、毎期の赤字が積み重なって累積赤字になります。
建物の賃貸料、従業員の給与、設備の維持費などの固定費が高すぎると、収益が増えない場合でも支出が膨らんでしまいます。この背景には、下記3.のビジネスモデルの問題や5. の外部環境の悪化、6.経営の非効率性などが考えられます。
2. 一時的な大きな損失
大規模な投資の失敗、不正会計、自然災害や事故による損失などで、ある年に大きな赤字が出て、それが繰り越されるケース。
3. 構造的なビジネスモデルの問題
市場の変化に対応できていない、競争力のない商品を売っている場合には、販売不振、過当競争などにより、企業が十分な収益を得られない場合、赤字が続くことがあります。このような根本的な経営戦略の失敗も原因になります。
4. 財務構造の脆弱性
借入過多で利息負担が重い、あるいは過剰な設備投資(投資の失敗)などにより、固定費が高すぎるといった財務面の問題も、利益を圧迫して赤字を招きます。
5. 外部環境の悪化
景気後退、原材料価格の高騰、為替変動、感染症や戦争など、外的要因の影響で利益が出なくなることもあります。 こうした要因が重なったり長引いたりすることで、累積赤字は大きくなります。再建にはコスト削減、事業の見直し、資金調達などの抜本的な対策が必要になります。
6.経営の非効率性
組織内の非効率的な運営、資金の適切な管理ができない場合、赤字が累積します。
債務超過の解消策
債務超過を解消するためには、いくつかの方法があります。以下に代表的な対策を挙げます:
1.増資
増資とは、企業が資本金を増やすことです。株式会社であれば、株式を発行して投資家から資金を集めることを意味します。増資して資本金や純資産を増やせば、応急処置的に負債を減らせます。増資の方法は以下のとおりです。
特に第三者からの増資を受けられれば、金融機関からの信用も高くなります。
増資に加えて債務再編を受けられる可能性も出てくるため、さらなる経営改善につながる可能性もあります。ただし、出資額や株式数によっては、出資相手に経営権が移るといった問題が出てくるので、注意しましょう。
2.遊休資産の売却
有価証券や、土地や建物、設備など企業が保有する資産を売却した利益によって債務超過を解消する方法もあります。
たとえば、長年にわたって保有していた土地の価格が上がり、含み益があるばあには、不動産を売却することで売却益が発生し、債務超過を削減あるいは解消できる場合もあります。
3.債務再編
債務再編とは、債権者と債務者が直接交渉を行い、債務の返済に関する条件などを緩和してもらうことをいいます。
債権者と交渉し、支払期限や利率などの条件はもちろんですが、返済する元本の金額も含めて合意が成立すれば、債務超過の解消に向けた一歩になることもあります。
一部の債務を免除してもらうことができれば、債務超過の解消に大きく前進できます。
4. 債務の株式化(DES)
債務を株式に転換することで負債を減らす方法があります。
DES(デット・エクイティ・スワップ)とよばれ、債権者がもつ債権と債務超過した企業の株式を交換する方法です。
デット・エクイティ・スワップは、債権者(お金を貸している人)が、その企業に対する債権を放棄(企業の借金の免除)する代わりに、株式を受け取るという仕組みです。
債権者にとっては、債務超過を改善した後、将来的に経営が改善されたタイミングで配当や売却益を得られる可能性もあります。
5. 経常利益の増加
コスト削減や売上向上を図り、利益を増やす。
6.事業を譲渡する
債務超過は、事業の譲渡で解消できる場合があります。
債務超過の会社の事業が売れるのか疑問に思われるかもしれません。しかし、以下のケースであれば事業譲渡が成立する可能性があります。
このような場合は、事業譲渡、あるいは会社分割などの方法でM&Aを実施することができます。
ただし、債務超過にある企業のM&Aは、「詐害行為(わざと財産を減少させて弁済を免れる行為)」とみなされるかもしれません。買い手に対しては、事業の現状やリスクをありのままに伝え、真摯に対応することが大切です。
7.法的手続きの活用
どうしても経営改善や資金調達が難しいときは、最終的な手段として、民事再生法や会社更生法を適用し、再建を目指す方法もあります。
手続きとしては、一旦裁判所に届出をしたのち、財産の処分、負債の返済計画、事業内容の見直しを進めていくことになります。
民事再生法は、個人や法人全般が対象です。経営陣はそのままで、計画に基づいて再生を進めていくことができます。
一方で会社更生法は、株式会社のみが対象です。経営陣はすべて退任した後、裁判所が選任した管財人によって再建が進められていきます。