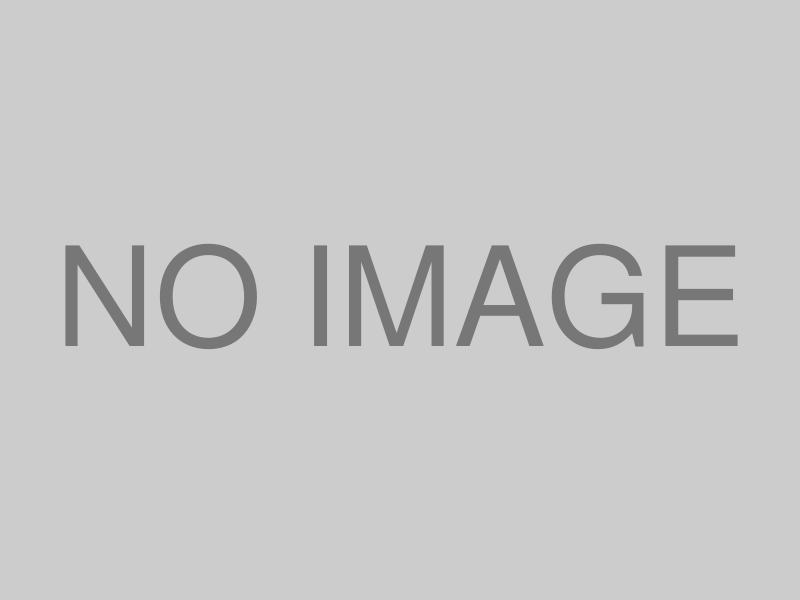青色申告と白色申告の違い メリット・デメリットについても解説
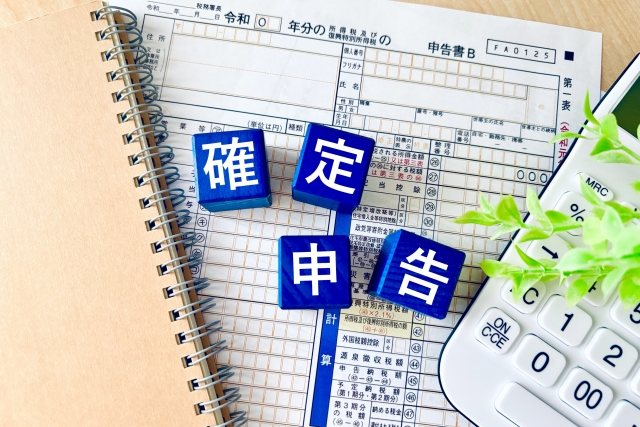
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
「白色申告」と「青色申告」との違いは、主に作成する帳簿と控除額にあります。
しかし、青色申告に比べると節税のメリットが少ないため、事業規模が大きくなる場合や事業所得が大きくなる場合には、青色申告への切り替えを検討する必要があると思われます。
「白色申告」は、受けられる控除は基礎控除のみになりますが、事前の届出が不要で、取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記帳するなど、簡易な記帳方法が認められています。
一方、青色申告なら、さまざまな税制優遇の特典が受けられます。 これらの特典を活用すれば、所得税や住民税の負担を軽減することも可能です。
ただし、事前の届出や、日々の一つ一つの取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて申告が必要です。
さらに、青色申告ができるのは「事業所得・不動産所得・山林所得」の場合に限られます。 よって、個人事業主であれば、青色申告を選択できますが、サラリーマンなどの給与所得や雑所得については、青色申告が選択できません。
以下で、両者の違いを解説します。
1.確定申告とは
確定申告は、1年間の所得を国に申告し、それに基づいて所得税や住民税を計算する手続きです。前年の1月1日から12月31日までの収入と経費を基に申告します。
一定の所得がある場合は所得税などを納めなければいけないため、確定申告をしなければいけません。
対象者は、フリーランス、自営業者、その他一定の条件に該当する給与所得者などです。
提出期間は、翌年の2月16日から3月15日までです。
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
「白色申告」と「青色申告」との違いは、主に作成する帳簿と税額計算上の控除額にあります。
「白色申告」は、受けられる控除は48万円の基礎控除(合計所得が2,400万円以下の場合)のみになりますが、事前の届出が不要で、取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記帳するなど、簡易な記帳方法が認められています。
一方、「青色申告」は基礎控除に加えて最大65万円の青色特別控除を受けることができたり、親族に支払う給与を必要経費に算入できたりするなど、節税のメリットが大きい制度です。ただし、事前の届出や、日々の一つ一つの取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて申告が必要です。申告方法は白色申告よりも煩雑ですが、節税効果が高いため、多くのフリーランスや個人事業主に利用されています。
2.白色申告とは
(1)概要
白色申告は、所得税の申告方法のひとつで、個人事業主やフリーランスが比較的簡単に利用できる方法です。青色申告と異なり、特別な事前手続きは必要ありませんが、税制上の優遇措置も少ないため、一般的には年間の所得が少ない場合に選択されることが多いです。
白色申告が向いているのは、事業を始めたばかりで収入や経費が少ない場合、あるいは、簡単な手続きや記帳を希望している場合、または、青色申告の特典を必要としない(控除や損失繰越が不要)場合です。
(2)白色申告の主な特徴
①事前申請が不要
白色申告を利用するためには、事前に税務署への申請や届出を行う必要はありません。そのため、開業直後の事業者や、初めて確定申告をする人でも手軽に利用できます。
これに対し、青色申告の場合には、「青色申告承認申請書」の提出が必要です。
②記帳義務
2014年(平成26年)以降、全ての個人事業主に記帳義務が課されています。
収入や支出の記録をつける必要がありますが、青色申告に比べて簡素な帳簿で対応できます。複式簿記ではなく簡易簿記や家計簿感覚の記録でも認められます。
具体的には、簡易帳簿や現金出納帳が用いられることが一般的です。現金売上・仕入については、日々の合計金額のみを一括記載することができます。
なお、これらの帳簿は、原則7年間保存する義務があります。
③税務上の特典が少ない
白色申告には青色申告で認められる特別控除や赤字の繰越といった特典がありません。
例えば、青色申告では最大で65万円の控除が受けられることがありますが、白色申告ではこのような控除はありません。
④提出書類が少ない
提出書類は比較的少なく、必要な内容をシンプルにまとめることができます。
主な提出書類は、確定申告書Bと収支内訳書です。
(3) 白色申告の適用範囲
青色申告と同様、事業所得、不動産所得、山林所得が対象です。
3.白色申告のメリット
(1)特別な手続きが不要
青色申告のように事前に承認申請書を提出する必要がないため、申告時点で必要な書類を準備するだけで済みます。
(2)白色申告者に係る「事業専従者控除額」
白色申告の場合、生計を一にする配偶者やその他の親族に支払った給与等を必要経費に算入することができません。
しかし、下記の(※1)の要件を満たす「事業専従者」が事業に従事している場合には、事業専従者控除として、配偶者は最高 86 万円、15 歳以上のその他の親族は最高 50 万円を必要経費として差し引くことができます。
(※1)事業専従者とは、次の要件のすべてに該当する人をいいます。
- ① 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
- ② その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
- ③ その年を通じて6ヵ月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(※2)青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人または白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
(3)帳簿づけが簡単で自由度が高い
帳簿作成が簡易な方法で対応でき、会計や簿記の知識がなくても申告しやすいため、事業開始直後や収入が少ない場合に適しています。家計簿感覚で収支を記録できるため、煩雑な経理作業を避けられます。
4.白色申告のデメリット
(1)青色申告特別控除が使えない
白色申告では、青色申告にある「青色申告特別控除(最大65万円)」が適用されないため、課税所得が増える可能性があります。
(2)損失の繰越控除ができない
白色申告では、赤字が出ても翌年以降の利益と相殺できません(損失の繰り越しができません)。
(3)家族への給与が経費にできない
青色申告では認められる「青色事業専従者給与」が白色申告では適用されません。
ただし、白色申告の事業専従者控除があり、一定額までは経費にできます。

5. 青色申告とは
青色申告とは、個人事業主やフリーランスが一定の条件を満たすことで、税制上の特典を受けられる申告方法です。主に事業所得、不動産所得、山林所得がある場合に選択できます。
青色申告は、税務署に事前に申請し、正確な帳簿を作成することが必要です。次に詳しく説明します。
(1)税務署への申請が必要
青色申告を行うには、事前に管轄の税務署へ「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
提出期限は、原則として、新たに青色申告の申請をする方は、青色申告をしようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
なお、新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)には、
業務を開始した日から2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
(2)帳簿の記帳が必要
青色申告では、正確な帳簿が必要です。帳簿のつけ方には、複式簿記と単式簿記(簡易帳簿)の二種類があります。そして、帳簿のつけ方の違いによって、下記のように青色控除額が異なります。
①複式簿記
65万円控除または55万円控除を受けるためには、正規の簿記の原則により記帳を行う必要があります。正規の簿記とは、複式簿記のことです。必要な帳簿は、仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳などです。
帳簿は、収入・支出を漏れなく個々に記録し、損益計算書と貸借対照表を作成する必要があります。
②簡易帳簿
簡易帳簿は、10万円控除の場合に認められます。必要な帳簿は、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳などです。主要簿(仕訳帳、総勘定元帳)は、必要ありません。
帳簿は、収入・支出を漏れなく個々に記録し、損益計算書(貸借対照表は不要)を作成する必要があります。
(3)期限内に申告を行う
確定申告の期限(通常は3月15日)までに正確に申告する必要があります。
6.青色申告のメリット
(1)青色申告特別控除
青色申告では、「青色申告特別控除」として10万円または65万円(55万円)の控除を受けることが可能です。控除額が大きいほど所得税の節税につながります。
具体的には、下記のすべての条件に該当する場合は、65万円の控除を受けることができます。
また、下記の①~③の条件のみに該当する場合は、55万円の控除を受けることができます。
10万円の特別控除は、①を満たし、②簡易帳簿による損益計算書を添付し、③法定申告期限内に確定申告書と青色申告決算書(損益計算書)を提出している場合に適用されます。
①不動産所得、事業所得、山林所得がある
②複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付
③法定申告期限内に確定申告書と青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表)を提出している
④仕訳帳および総勘定元を電子帳簿保存している、もしくはe-Tax(国税電子申告納税システム)を利用して確定申告を行う
国税庁参考サイト
(2)赤字の繰越控除
青色申告では、事業で赤字が発生した場合、その赤字を翌年以降の最大3年間繰り越して翌年以降の所得と相殺できます。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失を生じた年の前年に損失額を繰り戻し、前年分の所得を下げて還付を受け取ることもできます。
(3)家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)
青色申告者と生計を一にしている一定の親族が事業に従事している場合、その給与を経費として計上可能です(「青色事業専従者給与」と呼ばれます)。
なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける方は、扶養親族や控除対象配偶者になれないため注意しましょう。
青色事業専従者給与として認められる要件は、下記の通りです。
①給与を受け取った親族が、次の要件のいずれにも該当すること。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
②「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
③届出書に記載されている方法により支払われ、かつ、その記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
④青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。
提出時期は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2ヵ月以内)となっています。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
国税庁参考サイト
(4)少額減価償却資産の特例
青色申告であれば「少額減価償却資産の特例」を受けることができます。この特例を使えば、取得価格30万円未満の事業用資産を、購入した年度に一括で経費計上できます。
たとえば20万円の事業用備品を買った場合は、全額をその年の減価償却費として経費計上できます。
ただし、この特例の合計限度額は300万円なので注意する必要があります。
7.青色申告のデメリット
(1)帳簿作成が煩雑
色申告で55万円か65万円の特別控除を受けるには「複式簿記」で記帳する必要があります。そのため、白色申告よりも記帳作業が複雑になります。
(2)準備が必要
開始前に税務署へ申請手続きを行う必要があります。白色申告ではこの手続きは不要です。
(3)帳簿書類とその保存に手間がかかる
青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
これらの帳簿および書類などは、原則として7年間保存することとされていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。
5年間の保存でよい書類には、例えば、請求書、見積書、納品書、送り状などがあります。
8. まとめ
以下に、青色申告と白色申告の違いをまとめます。
(1)事前申請の必要性
青色申告をするには、事前申請が必要です。
一方、白色申告であれば事前申請は不要です。 青色申告の申請をしなければ、自動的に白色申告となります。青色申告の申請をした場合でも、あとから青色申告をやめて白色申告を選ぶことは可能です。
(2)青色申告特別控除
最大65万円の控除が受けられる「青色申告特別控除」は、白色申告では、適用を受けることができません。
(3)帳簿の種類や記帳方法
白色申告の帳簿は、基本的に簡易簿記で記帳が可能で、複式簿記は不要です。
青色申告の帳簿は、55万円・65万円の控除の場合は、複式簿記で記帳することが条件となります。 複式簿記とは、取引を借方と貸方に分けて記録する方法です。
青色申告の場合でも、10万円控除であれば、基本的に簡易簿記です。
(4)親族への給与
白色申告では一定の親族へ支払った給与のうち配偶者は86万円まで、その他の親族は50万円までしか控除できませんが、青色申告では届け出さえしていれば全額控除できます。
(5)少額減価償却資産の特例
白色申告では、、原則として10万円以上する備品や器具を購入した場合、一度に必要経費として計上できず、減価償却資産として一定のルールに則り毎年分割して経費に計上します。しかし、青色申告では、30万円未満の資産は一時に経費として計上することもできます(年間総額が300万円に達するまで)。
(6)損失の繰越控除ができない
白色申告では、赤字が出ても翌年以降の利益と相殺できません(損失の繰り越しができません)。青色申告を選択している場合には、赤字が発生した場合には、翌年以降の最大3年間にわたって損失を繰り越すことが可能です。
| 項目 | 白色申告 | 青色申告 |
| 事前申請 | 不要 | 必要 |
| 特別控除 | なし | 最大65万円(55万円)または10万円 |
| 記帳の複雑さ | 簡易的な帳簿でOK | 複式簿記が必要(65万円または55万円控除を受ける場合) |
| 親族への給与 | 86万円まで、または50万円まで | 要件を満たせば、全額OK |
| 少額減価償却資産の特例 | なし | あり |
| 赤字の繰越・繰戻 | 不可 | 可能 |