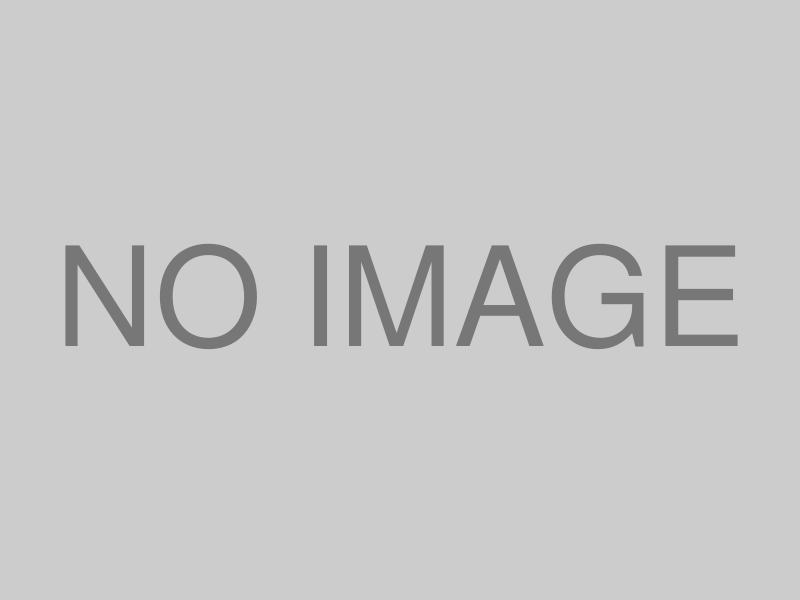源泉所得税の納期の特例とは
目次
源泉徴収制度
事業者が、給与や報酬などを支払う支払いの際、所得税などを天引きすることになっています。天引きした事業者(源泉徴収義務者)は、給与や報酬を受け取る側に代わってこの天引きした所得税を国に納めます。このことを源泉徴収といいます。源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めることになっています。
源泉徴収義務者とは
上記のように、所得税(および復興特別所得税)を天引きして、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収義務者となる者は、会社や個人だけではありません。給与などの支払をする学校や官公庁、人格のない社団・財団なども源泉徴収義務者になります。
また、給与所得について源泉徴収義務を有する個人以外の個人が支払う弁護士報酬などの報酬・料金については、源泉徴収をする必要はありません。
例えば、サラリーマンが確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。
納期の特例とは
上記のとおり、源泉徴収した所得税は、翌月10日までに納付することが原則です。しかし、給与の支給人員が常時10人未満の場合は、源泉徴収した所得税および復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを納期の特例といいますが、中小企業にとっては、大変便利な制度です。
納期の特例の適用条件
納期の特例を適用できるのは、給与の支払を受ける人の人数が常時10人未満である場合に限られます。支給人員には、正社員のほかに役員や常時雇用するパートやアルバイトも含まれます。
納期の特例の対象は二つ
この特例の適用の対象となるのは、下記の二つに限られています。
①給与や退職金から源泉徴収をした所得税(および復興特別所得税)
②税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税(および復興特別所得税)
納期の特例の期限は半年ごと
この特例の適用を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限となります。
①1月から6月に従業員から徴収した分・・・7月10日が納期限
②7月から12月に従業員から徴収した分・・・1月20日が納期限
(注)これらの納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納付期限となります。
納期の特例の手続き
この特例の適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(以下「納期の特例申請書」といいます。)を提出することが必要です。
この納期の特例申請書の提出先は、納税地の所轄する税務署長です。
税務署長から納期の特例の申請について却下の通知がない場合には、この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、申請書を提出した月の翌月に源泉徴収する所得税および復興特別所得税から、納期の特例の適用の対象になります。
具体例
納期の特例申請書を提出した月が2月中の場合は、2月支給分の納期限は3月10日となり、3月~6月支給分の納期限は7月10日となります。
支給人数が10人以上になった場合
なお、給与の支給人員が常時10人以上となり、源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出することが必要です。この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期の特例の期間から納期の特例の承認の効力が失われます。
具体例
<源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書を提出した直後の納付期限等>
届出書を提出した日が3月中の場合は、1月~2月支給分の納期限は4月10日(※)、3月支給分の納期限は4月10日、
4月以後支給分の納期限はは、翌月10日で原則どおりとなります。
※ 1月から2月分は、納期特例分の徴収高計算書を使用し、3月分以降は、一般分(毎月納付用)の徴収高計算書を使用します。
国税庁参考サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm
まとめ
源泉所得税の納期の特例は、本来なら毎月納税しなければならない源泉所得税を、一定の条件を満たせば、年2回に分けて納入することがでるという制度です。
納期の特例を受けようとする事業主は、事前に申請する必要があります。
納期の特例の適用を受けると、具体的には、1月~6月分までの6ヶ月分を7月10日まで、7月~12月分までの6ヶ月分を1月20日まで、の年2回に分けて納付することができます。
従業員が10人未満の中小企業においては、積極的に活用しましょう。
さらに、住民税の納期の特例と合わせて利用すると、一層の経理の合理化ができます。
なお、住民税の納期の特例につきましては、下記の記事をご覧ください。