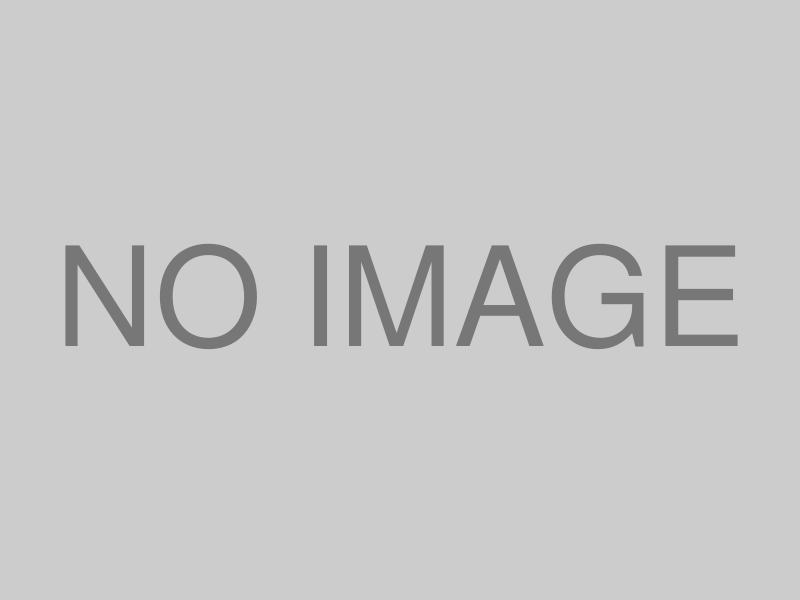デット・エクイティ・スワップ(DES)とは
目次
デット・エクイティ・スワップ(DES: Debt Equity Swap)とは、企業の債務(借金)を株式に転換する手法で、債務の株式化ともいいます。主として企業の財務体質を改善し、経営の安定化を図るための企業再建手法です。金融機関が経営不振の取引先を支援する目的で使われるケースが一般的です。
DESにおいては、債権者が保有する企業に対する債権(貸付金など)を放棄する代わりに、その企業が新たに発行する株式を受け取ることで、債務が消滅し、代わりに資本が増加します。つまり、企業の自己資本比率が向上することになります。
一方、債権者側は、債務と交換で株式を受け取ることにより、新たに株主として経営に影響力を持つことができます。
DESの目的
DESは、以下のような目的で導入されることが多いです。
1.債務超過の解消
多額の借入金によって債務超過に陥っている企業が、DESにより債務を資本に変えることで、貸借対照表上の自己資本を増やし、債務超過状態を解消することができます。
2.財務の健全化と信用力の向上
負債比率の低下や自己資本比率の向上によって、金融機関からの追加融資を受けやすくなるなど、企業の信用力を改善する効果があります。
3.キャッシュフローの改善
借入金の返済や利息支払い義務がなくなるため、企業のキャッシュフローが改善し、事業活動に充てる資金が確保しやすくなります。
DESの実施方法
DESの一般的な手順については、『現物出資型』と『金銭出資型』の2種類があります。
1.現物出資型
現物出資型とは、債権者が、貸付金という現物を出資することになります。そして、現物出資された債権に応じて株式が発行されます。現物出資型のデットエクイティスワップでは、債権者と会社側でDESの実行を合意したうえで、第三者割当増資の手続きを実施します。DESといえばこちらの現物出資型を指すことが一般的です。すでに借入金が発生していますので金銭の移動はなく、帳簿上の振替処理で完結するためスムーズに手続きが完了します。
2.金銭出資型
金銭出資型は、債権者がまず増資に応じ、金銭を債務者に払い込み、債務者は、その払い込まれた金銭を借入金返済に充てるものです。その後、債務者は債権者に対してその金額に相当する株式を発行します。
現物出資型と同様に株式が発行される点では結果が同じですが、金銭出資型の場合は第三者割当増資の手続きと共に債務弁済手続きが必要です。
DESの手続き
DESは、通常、以下のような手続きを経て実施されます。
1.債権者との合意形成
債務を株式に転換するには、まず債権者と企業との間で合意が必要です。債権の評価や株式発行価格、発行株数などについて交渉が行われます。
2.新株の発行
企業は、合意に基づき第三者割当増資などの方法で新株を発行し、債権者に割り当てます。この際の株式の発行価格は、時価や企業価値などを基に公正に決定される必要があります。
3.法的手続き
株式の発行にあたっては、会社法上の手続き(株主総会や取締役会の決議など)や、金融商品取引法上の規制(大量保有報告、インサイダー取引防止など)に則る必要があります。
4.登記手続き
株式発行後、商業登記を行い、会社の資本構成の変更を正式に記録します。これには、必要な書類の準備や法的手続きが含まれます。
デット・エクイティ・スワップの効果
デット・エクイティ・スワップの効果としては、次のようなことが挙げられる。
・財務体質の改善
債務者にとっては、負債を圧縮し、資本を増大することにより財務体質の改善をはかることができます。
・経営者のモラルハザードの抑制
債権者にとっては、債権の代わりに債務者の株式を保有することで、債権者が株主として企業再建にコミットすることができることから、経営者のモラルハザードを一定程度抑制する効果が見込まれます。
・株式の価値向上
債務者が将来、無事再建できたときには、株式の価値が高まることが見込まれます。株式価値向上が期待できるなら、債権者にとっては、債権放棄よりも好ましい方法と考えられます。
DESのメリット
債務者側のメリット
負債が減少し、利息の支払い負担が軽減されるため、キャッシュフローが改善します。
また、自己資本の金額が増え、負債の金額が減ることで、自己資本比率が向上します。
そして、財務状況が良くなることで、新たな資金調達がしやすくなります。
債権者側のメリット
株式を保有することで、企業の再建が成功した場合にキャピタルゲインや配当収入を得る可能性があります。
DESのデメリット
債務者側のデメリット
債権者が株主となるため、経営への干渉が増える可能性があります。
また、資本金の増加により株式配当という形で新たな資本コストが発生する可能性があります。
DESにより資本金が増えた場合は、法人税や法人住民税の負担が増える場合もあります。
債権者側のデメリット
貸付金がある場合、債権者は利息による収入を得ることができますが、貸付金を株式にすることによって利息収入が減少します。株式の配当金や売却益で得られる利益はありますが、債務者の状況によってはなくなることもあります。
債権が株式に変わることで、回収順位が後回しになり、リスクが高まる可能性があります。DESを行ってもなお経営再建できず債務者が倒産してしまった場合、株式分の金額を回収することが難しくなります。債権と株式では、債権のほうが回収順位が先です。債権への支払いに会社の資金を回してしまうと、株式に対する支払い分まで残らない場合があります。 この手法は、特に経営不振に陥った企業や事業承継の場面で活用されることが多いです。
中小企業の事業承継対策としての効果
事業承継では、資産だけでなく債務も後継者に引き継がれます。会社に債務が残っている状態で事業承継を行うと、返済の負担が後継者に重くのしかかります。DESによって債務を減らしてから事業承継を行うことで、後継者のスタートアップ時の負担軽減につながります。
また、相続対策で利用されることもあります。
中小企業では、役員からの資金借り入れによって運転資金確保している会社が多く見られます。
会社の借入金が社長個人からのものである場合、社長に相続が発生したとき、これは貸付金として相続財産に計上されます。
この場合、相続人は実際返ってくる見込みが薄い貸付金のために多額の相続税を支払うことになりかねなません。
相続税の評価では、貸付金は額面で評価されますが、株式は時価評価されるという特徴があります。
このようなケースでは、DESにより会社に対する貸付金を株式に転換することで、相続税評価額が減少することもありえます。
おわりに
DESは、企業の財務再建における有力な手法であり、特に債務超過や資金繰りに苦しむ企業にとって、再建の道を切り開く可能性を持っています。一方で、その実施にあたっては株主構成や経営体制への影響、法的・会計的な取り扱いなど、慎重な検討が必要です。
DESは単なる財務操作にとどまらず、債権者と企業との信頼関係や、長期的な経営ビジョンの共有が求められる再建戦略の一環として位置づけられるべきでしょう。